H・R・マクマスターの『戦場としての世界』(2021年)を読みました。
トランプ政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めた著者が、中国、ロシア・イラン・北朝鮮などの脅威に対して、自らの経験に基づいて綴った超ハードな国際政治・外交の現代史です。
前回の投稿(ロシア)に次いで、今回は中国のトピックを取り上げます。
平和な日本に住んでいる限り、決して知る機会のない(メディアでも報道されない)衝撃の事実の数々。。。私自身の生涯ベスト本に入る1冊です。
以下に本著の内容を所感をまとめました(太字は本文より引用)。
1. H・R・マクマスター
『戦場としての世界』の著者H・R・マクマスターは、1962年生まれのアメリカ合衆国の退役軍人です。
前回の投稿より一部抜粋して再掲載します。
陸軍能力統合センター長、陸軍訓練教義コマンド 副司令官、ドナルド・トランプ政権の国家安全保障問題担当大統領補佐官を歴任しました。
H・R・マクマスター(写真:ロイター/アフロ)
マクマスターは軍人として34年間にも及ぶ陸軍勤務(もちろん命を賭けた実戦も含む)を経験しているだけでなく、軍人は歴史を学ぶべきという信念に基づいて、ウエストポイント(陸軍士官学校)を卒業後にノースカロライナ大学で歴史学の博士号を取得しています。
2. 『戦場としての世界』
こちらも前回の投稿より一部抜粋して再掲載します。
日本に迫られる決意と覚悟!
戦略的ナルシシズムから脱却せよ!
安全保障担当大統領補佐官を務めた卓越した戦略家が、中国、ロシアなどの攻勢・企てに警鐘を鳴らし、 世界のリアリティを伝えます。
【目次】
第1部 ロシア
第1章 恐れ、名誉、そして野望:プーチンの西側に対する追い落とし作戦
第2章 プーチンの策略をかわす
第2部 中国
第3章 統制への執着:中国共産党が突き付ける自由と安全に対する脅威
第4章 弱みを強みに変える
第3部 南アジア
第5章 1年限りの戦争が20回もの繰り返しに:アメリカが南アジアに抱く幻想
第6章 平和のための戦い
第4部 中東
第7章 いとも簡単だなんて誰の入れ知恵?:中東への見方、楽観からあきらめに
第8章 悪循環を断つ
第5部 イラン
第9章 悪しき取引:イランの40年に及ぶ代理戦争と成立しなかった和解
第10章 選択を迫る
第6部 北朝鮮
第11章 狂気の定義
第12章 それらがなければ、彼はより安全に
第7部 アリーナ
第13章 新たな競争の舞台へ
3. 中国
中国共産党に国際法や貿易、商業に関するルールに従う考え方はない
中国は自由で開かれた社会に対する脅威であり、その政策はルールに基づく秩序に取って代わる閉鎖的で権威主義的なモデルを積極的に世界に広めている
いきなり真髄に入りました
が、この見解には個人的に賛同する一方、以下のブログに書いた通り、中国側の主張や考え方にも耳を傾けるべきでは?
上海にいる中国人の友人宅での滞在は、グワンシと呼ばれる中国独特の人間関係や、富への考え方、そして(民間資本主義と対比した)国家資本主義社会についても深く考える良い機会になりました。
グワンシについて、ブログから以下抜粋します
・中国人の濃い人間関係を「グワンシ」と呼びます
・グワンシは、幇を結んだ相手との密接な人間関係のことを指し、中国独特のものです
・幇とは、朋友の意味で、論語で「同門の友」を意味します
・いったん中国人とグワンシという間柄になると、絶対的な信頼を置いた付き合いとなります
・逆に、グワンシではない相手とは、自分とは関係のない存在です。平気で裏切ろうが何をしようがお構いなしです。相手が内輪かどうかで決定的な違いがあります
・相手がグワンシの間柄であれば、自分にできる最高のもてなしをする、それが相手への信頼の唯一の証になるのです
・グワンシのもう一つの特徴は、相手を裏切ることで得をする機会があれば、それを躊躇なく実行しても咎められないという点です
・日本人の道徳観では、とても受け入れがたい感覚ですが、中国ではこれが常識なのです
・そして、グワンシの間柄でのルールは、社会や国家のルールを超越するということです
・これが、いわゆる中国が法治国家ではなく、人治国家であるという背景になっています
(ブログの抜粋おわり)
グワンシの詳細については「言ってはいけない中国の真実」という本を参照ください
それまでは中国が西側を踏み台に強大化していくのは必然的な現象であり、これに挑戦せず、適合するのが最良の対応だとみなしていたが、止めてしまったのである
新しい政策では我々が中国と競争関係にあると位置づけた
このような米国の大きな政策変更によって、アメリカにとって中国は、冷静終結後の新しい仮想敵国となったわけです。
逆を返せば、米国が現在のような圧倒的な国際優位性を誇っておらず、たとえばイギリスやドイツといったヨーロッパの強国レベルに留まっていたならば、中国と競争関係にあるという政策は取りようがなかったでしょう
1990年代以降、アメリカの対中政策には、進路を誤らせる戦略的ナルシシズムのすべての要素が表れていた
希望的観測、ミラー・イメージング(つい相手を自分と同じと見なしてしまう傾向)、確証バイアス(反証材料を無視する傾向)、そしてアメリカが用意した「脚本」に他の国も準拠して行動するだろうという思い込みなどである
鋭い洞察だと思います
アメリカは慢心で横柄な態度を取るというのが通説で一部は正しいのですが、同時に、このような自己診断力と軌道修正力を兼ね備えている点は、(日本を含む)他国にはない強みでもあります
「中国の指導者たちの政策と行動を理解するためには「歴史的な視点は(なくても構わない)贅沢品どころか必需品である」
「軍人は歴史を学ぶべき」というのは、本著のメインテーマです
共産党はたゆまず「中華民国の偉大な復興」を追い求めてゆく
中国は世界の中心的な位置を占めて人類により大きな貢献をする
中国の王朝は強大な「世界の真ん中にある国」だった
紫禁城は1368年から1644年まで276年にわたって全土を統治した明王朝の時代、すなわち中国の一つの黄金期とみなされ、経済、領土、そして文化のいずれも点でも頂点を極めた時代に建てられた
かつての紫禁城は、外国人たちが皇帝の権威を前に敬意を表し、貢物を捧げ、そして皇帝が彼らに与えるかもしれない特権を懇願するためにやって来る場所だった
このようなノスタルジーが果たして現在の中国共産党に浸透しているのかは不明です
しかし、人類の長い歴史のなかで一時的な栄華を極めた他の多くの国々(オスマン帝国、ムガール帝国など)と違い、中国には再びその世界覇権を握れる可能性が高いのは紛れもない事実です
紫禁城を完成させた明朝の永楽帝こと朱棣(しゅてい)は、モンゴル族の再度の侵攻の可能性よりも、内なる危険性を強く気にかけていた
彼は先手を打って儒学者や官僚の反対派を抑え込んだ。忠誠でないと疑われた本人だけではなく、女性や子供を含む親族すべての処刑を命じた
犠牲者たちの中には後に4人の殉教者として知られる儒学者たちがいた
その一人、方考儒は9代にわたる親族を皆殺しにすると脅されると「10代でも結構だ」と聞えよがしに答えた
血族全員と門下生、仲間まで合わせて873人が殺害された
まさにスターリンや北朝鮮にも劣らない粛清ぶりですね。。。
しかしちょっと待ってください
同じ時期にヨーロッパ諸国でも、似たような権力者による粛清は行われていなかったのでしょうか。。。?
例によって、AIのCoPilotで調べてみたところ、フランス革命時代の粛清:ロベスピエール派による恐怖政治(1793年 - 1794年)や、テルミドールのクーデターでのロベスピエール派に対する粛清(1794年)といった歴史的事実が見つかりました
ロベスピエール派による恐怖政治は、1793年9月から1794年7月までの約10ヶ月間にわたって行われました。この間に、パリだけで約1万4000人、フランス全体では2万人以上がギロチンにかけられました。また、司法手続きを省略した死刑や獄中死も多く発生し、犠牲者の総数は4万人を超えるといわれています。
フランスのほうが中国よりも遥かに残虐だったんでは??
毛沢東は秩序を破壊し、革命を続けて混乱をもたらした。一方、習近平は儒教の道徳的秩序を思い起こさせて統制を保ち、人びとに恭順を促す
言うまでもなく、毛沢東の文化大革命は、数千万人!の犠牲者という中国全体に莫大な被害を与えた大失敗だったわけですが、現在の中国主導部はそれに触れずに「なかったこと」にしているんですね
習は中国共産党の歴史の解釈に手を加えてより穏健なものにした。新しい解釈では党は3段階で進歩してきた
第一に、毛沢東は屈辱の世紀に終止符を打った
第二に、鄧小平と彼の後継者たちは富を創出した
第三に、習近平は中国の偉大さを取り戻した
毛沢東を圧政者ではなく救世主とした周の描写は、歴史の改竄以上に相当する行為である
繰り返しになりますが、「軍人は歴史を学ぶべき」という本著の信念に反する行為ですね。。。
習と彼の家族は文化大革命期に肉体的にも精神的にも虐待を受けた。父親は党の上級幹部だったが、投獄され、迫害された。紅衛兵たちは習の実家を略奪し、家族は逃げ出すしかなかった。姉の1人は困窮の中、死亡した
中国共産党にこれほどまでの仕打ちを受けた身として、習が語ることはほとんどないどころか、その非難を渋る心理状態はちょっと想像がつきません。。。
果たしてどこまでが事実なのか不明ですが、少なくとも、習以外にも、現在の党の上層部にいる同時代のメンバーたちは、強制労働などを経験しているわけですから、彼らが少なからず中国共産党への絶対的な忠誠から口を閉ざしている(もしくは強制的に閉ざされている)のは事実のようです
中国の権威主義的な資本主義は多大な汚職、腐敗の機会を生み出し、そして共産主義国を自称するどの国もこれまで見たことがないほど分厚いブルジョア階級を作り出した
確かに以前の中国はそうだったかもしれませんが、現在の習近平の体制下では、汚職は重罰が課せられています。
日本で自民党の政治資金パーティー収入の裏金問題が取り沙汰されていますが、現在の中国で同じことが起こったら、議員であろうが間違いなく関係者は禁固を含む重罰を科せられるでしょうか?
AIのCoPilotに訊いてみました
自分
習近平の汚職や贈賄に対する厳しい処罰は、もし中国で今の日本の自民党の政治資金パーティー収入の裏金問題と同様のことが発覚したら、関係者は禁固刑を含む厳しい重罰を科せられるでしょうか?それとも中国も中枢の政治家たちは習近平体制下では昔と同様、賄賂や汚職は罰せられることなく横行しているのでしょうか?
Copilot
こんにちは、Copilotです。ご質問にお答えします。
習近平国家主席は、2012年に就任以来、反腐敗運動を展開し、多くの高官や軍人を処罰してきました。習氏は「ハエもアリも処罰」というスローガンで、小さな汚職も大きな汚職も容赦なく摘発すると表明しています1。習氏は自らの権力基盤を固めるためにも、反腐敗運動を続けるとみられます。
一方で、中国の汚職問題は根深く、完全に解決されたとは言えません。中国の政治体制は、共産党の一党独裁であり、司法やメディアの独立性が低く、権力のチェックやバランスが不十分です。また、科挙制度の影響で、政治家や官僚は試験に合格することが最優先となり、社会問題の解決に無関心となる傾向があります2。さらに、経済発展に伴う格差や不公平が、汚職の温床となっています。
したがって、もし中国で日本の自民党の政治資金パーティー収入の裏金問題と同様のことが発覚した場合、関係者は禁固刑を含む厳しい重罰を科せられる可能性は高いと思われます。しかし、それは習氏の権力闘争の一環である可能性もあります。また、中国も中枢の政治家たちは習近平体制下でも、賄賂や汚職を隠蔽したり、見逃したりすることがあると考えられます。中国の腐敗の深刻さは、歴史的にも現代的にも、政治経済の大きな不安定要因であると言えます。
やはり。。。!
もちろん、グワンシの間柄でのルールは社会や国家のルールを超越するものなので、習近平に親密な関係を持っていればセーフとなる可能性もあると思いますが。。。
中国は海外向けには権威主義的な資本主義のシステムを広めると決意している。目的は、民主過ぎの原則と自由主義型の経済慣行を遵守する国を踏み台にして、中国の権力と影響力を拡大することだ
中国問題のすべては、まさにここに帰着します
自国で国家資本主義が閉じていればともかく、自由主義型の経済では経済成長の源泉のひとつは貿易なので、外国と取引せざるを得ない
そうなると、外国の影響が自国に流入することが避けられず、かつてのモンゴル民族の侵入と同じことが、武力ではなく人民の力として中国を内部から崩壊させてしまう恐れがあります
Newsweekの年末特集号には「邪悪で安定した悪夢の習路線は続く」という記事が掲載されています
結局、資本主義と自由主義に基づいた経済成長をグローバルに進めてゆくためには、全世界のすべての大国が、同じイデオロギーで揃っていないと機能しないということですね。。。
中国の指導者たちが目指しているのは、かつて皇帝たちが周辺諸国に君臨するために利用した朝貢体制の現代版の確立である
・中国製造2025:中国を外国に依存しないほぼ自立した科学と技術革新に強国に育てる
・一帯一路構想:総額1兆ドルを超す資金をインド太平洋とユーラシア大陸の全域までを対象とした新たなインフラ整備事業に投じる
・軍民融合(MCF):すべての企業が情報収集に協力しなければならない(2017年)
2020年には一帯一路構想のプロジェクトで融資を受けている33か国で過剰債務のリスクが高まり、貧困な8か国(パキスタン、ジブチ、モルディブ、ラオス、モンゴル、モンテネグロ、タジキスタン、キルギス)では債務が持続不可能な水準まで膨らんだ
スリランカは中国の国有企業に99年間貸与する契約への署名を余儀なくされた
軍民融合の国家情報法は強烈なもので、すべての中国国民は、国家の諜報活動を行う義務があると明記しています
つまり、すべての中国国民は、国の命令の元にスパイ活動を行う責務があるということです
中国のサイバー空間での悪意ある行為で被ったアメリカの経済的損失は2016年だけで1090億ドルに上った
中国は途轍もない規模でハッキングを継続しており、その恐るべきサイバー攻撃の能力が明らかになった。中国の国家安全省は、APT10として知られるハッカー部隊を使って、金融、情報通信、家電、衣料の業界の米企業やNASAと国防総省の研究施設を標的に定めている
アメリカのベンチャー・キャピタルやプライベート・エクイティは量子コンピュータ、AI、その他の技術の研究・開発を手掛ける中国企業に多額の出資をしているが、これは人民解放軍のビジョンの実現を手助けしていることでもある
これは難しい問題ですね、マネー自体には色はついていないので、利益を生むところに必然的に流れ込んでしまうので、「人民解放軍のビジョンの実現を手助けすることになるので中国への投資は控えましょう」というメッセージは効果がほとんどありません
1970年代になって中国はニクソン大統領からの関係再開の提案を受け入れた。両国には共通の敵であるソ連が存在したからだ
しかし、ソ連の崩壊で「敵の敵は友」という概念が崩れて、アメリカの中華人民共和国との関係は、アメリカが中国を変えられるという希望的な観測に基づくものに戻ってしまった
国力の推移が世界のバランスを崩すという典型例ですが、人も企業も国もみな未来永劫にわたって流動的で、同じ状態にとどまることは有り得ない(技術的にはエントロピーの原理に反する)ので、大国同士の衝突というのは未来永劫に地球からなくなることはないのだろうと悲観的な気分になってしまいます
台頭する国(中国)と衰退する国(アメリカ)の間では軍事衝突が起きる可能性は高い
しかし、そのどちらでもない中間を見つけ出すことが罠の回避につながる
私は中国側のカウンターパートたちと協議した際に、公正に競争することこそが対決せずに済む最良の手段だと説明した
中国が「公正に競争」することは有り得ないので、このアメリカのスタンスは、劣勢に立たされている側の窮余の策と捉えられるでしょう
米国が中国をロシア以上に脅威と捉えているのは、さまざまな分野(テクノロジー、経済、国家安全、軍事力)で中国に抜かれる日が近いという危機感を抱いているからでしょう
4. まとめ
ロシアが米国に対して挑戦するがごとく、アメリカは中国に対して今後も挑戦を続けなければならず、それは、中国の国力が衰退するまで徹底して競争することしか選択肢はないように思えます。。。
ということで、『戦場としての世界』次回のトピック③は「中東」です。
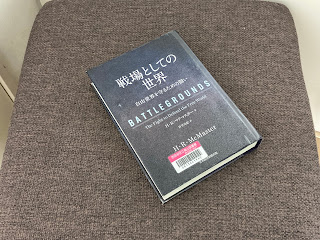







コメント